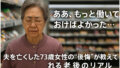介護と聞くと「お金がかかりそう」「制度が複雑そう」と感じる人も多いですよね。
でも、日本の介護制度は、公的な仕組みで支え合う仕組みになっています。
この記事では、厚生労働省のデータをもとに、
中高生にも理解できるように「介護保険の基本」と「利用にかかる費用」をやさしく解説します。
👉 後半の記事では、実際に「年金+貯金で何年持つか?」のシミュレーションも紹介します。
介護サービスとは?
介護サービスとは、高齢になって日常生活の一部に手助けが必要になったとき、食事・入浴・排せつ・リハビリなどをサポートしてくれる公的な制度です。
65歳以上なら、病気やけがが原因で介護が必要になったときに「介護保険」を使ってサービスを受けることができます。
利用者が払うのは“1割〜3割”だけ
介護サービスを使ったときの自己負担は、原則1割(所得が多い人は2割または3割)です。
たとえば:
-
1万円分のサービスを受けた場合
→ 支払うのは1,000円
(2割なら2,000円、3割なら3,000円)
つまり、残りの7〜9割は「介護保険」でまかなわれています。
利用者の負担が重くなりすぎないように国が支えている仕組みです。
自宅で介護を受けるときの費用
自宅で介護サービスを利用する場合(訪問介護やデイサービスなど)は、
「要介護度」ごとに使える金額(支給限度額)が決まっています。
| 要介護度 | 利用上限 (月) |
自己負担 (1割の場合) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約50,000円 | 約5,000円 |
| 要支援2 | 約105,000円 | 約10,500円 |
| 要介護1 | 約168,000円 | 約16,800円 |
| 要介護2 | 約197,000円 | 約19,700円 |
| 要介護3 | 約270,000円 | 約27,000円 |
| 要介護4 | 約309,000円 | 約30,900円 |
| 要介護5 | 約362,000円 | 約36,200円 |
💡 限度額を超えてサービスを使うと、その超過分は全額自己負担になります。
施設に入るときの費用
介護施設(特別養護老人ホーム=特養など)を利用する場合は、
介護サービス費以外にも居住費・食費・日用品費がかかります。
要介護5の方の例(月あたり)
| 費用項目 | 多床室 (相部屋) |
個室 (ユニット型) |
|---|---|---|
| 介護サービス費 (1割負担) |
約26,000円 | 約29,000円 |
| 居住費 | 約27,000円 | 約62,000円 |
| 食費 | 約43,000円 | 約43,000円 |
| 日用品など | 約10,000円 | 約10,000円 |
| 合計 | 約12万円 | 約18万円 |
💡 個室は快適ですが、費用は毎月3〜6万円ほど高くなります。
特養ではおむつ代はかからないのが一般的です。
🧾 所得が少ない人を助ける「補足給付」制度
年金や貯金が少ない人には、
「介護保険負担限度額認定制度(補足給付)」という制度があります。
所得や資産が一定以下であれば、食費と居住費が軽減されます。
| 段階 | 主な対象 | 預貯金の上限(単身) | 年金+所得 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者など | 制限なし | – |
| 第2段階 | 非課税+ 年金80万円以下 |
650万円以下 | 〜80万円 |
| 第3段階① | 非課税+ 年金80〜120万円 |
550万円以下 | 〜120万円 |
| 第3段階② | 非課税+ 年金120万円超 |
500万円以下 | – |
| 第4段階 | 課税世帯 | 対象外 | – |
この制度を使うと、
-
食費:1,445円 → 650円
-
居住費(個室):2,066円 → 880円
➡ 月に約6万円の軽減も可能です。
高額介護サービス費制度
月々の介護費用が高くなった場合、
一定の上限を超えた分が介護保険から払い戻しされます。
| 区分 | 月の自己負担上限 |
|---|---|
| 非課税世帯 | 15,000〜24,600円 |
| 課税世帯(年収770万円未満) | 44,400円 |
| 高所得世帯(年収1,160万円以上) | 140,100円 |
まとめ
介護保険は、だれでも安心して老後を迎えるための「支え合いの制度」です。
しかし、仕組みを知らないままにしておくと、思わぬ出費につながることも。
💬 まずは「制度の基本」を理解しよう。
そして次の記事で紹介する「年金+貯金のシミュレーション」で、
自分の将来を“数字で見える化”してみましょう。
👉 続きはこちら
💴 年金+貯金で何年持つ?介護費用シミュレーション完全版