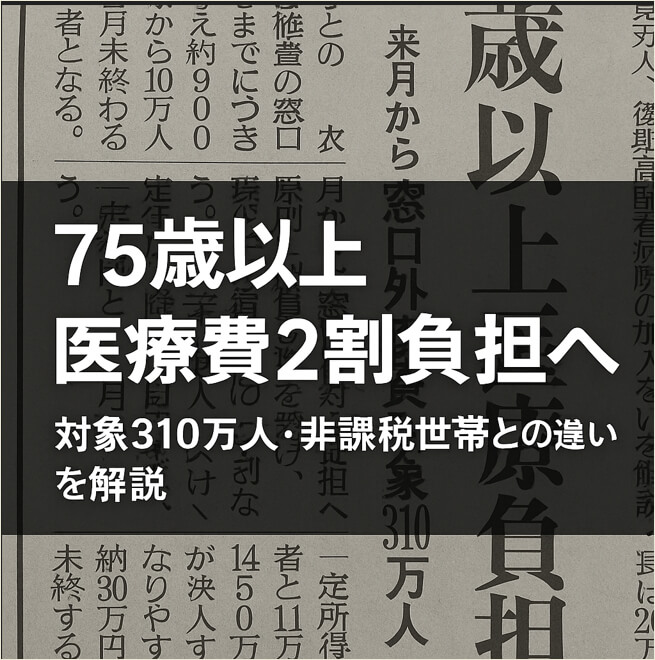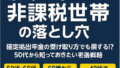2025年10月から、75歳以上の外来医療費の窓口負担が一部で 1割→2割 へ拡大されます。
-
対象者:約310万人(後期高齢者医療制度の加入者のうち)
-
従来:原則1割負担(現役並み所得者は3割)
-
今回:一定所得以上の人は 2割負担 へ
-
月平均で 約9,000円の負担増 と試算
👉 背景には高齢化による医療費の増大と、現役世代の負担軽減があります。
2. 今後起こりうること
今回の改正は“始まり”にすぎません。今後は以下が想定されます。
-
2割負担の対象拡大
所得基準が下がり、より多くの高齢者が対象に。 -
3割負担世帯の増加
現在も「現役並み所得」なら3割負担。対象拡大の可能性大。 -
年金控除・医療控除の縮小
課税対象者が増え、非課税世帯から外れる人が出やすくなる。 -
保険料のさらなる増加
国民健康保険料・介護保険料の上昇は避けられない。
3. 2割負担でどれだけ増える?シミュレーション
| 月の医療費総額 | 1割負担 | 2割負担 | 差額(1か月) | 差額(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | +1,000円 | +12,000円 |
| 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | +2,000円 | +24,000円 |
| 30,000円 | 3,000円 | 6,000円 | +3,000円 | +36,000円 |
| 50,000円 | 5,000円 | 10,000円 | +5,000円 | +60,000円 |
👉 慢性疾患で毎月2〜3万円の外来通院がある人は、年間3〜4万円の負担増。
4. 「非課税世帯」だとどう違う?
非課税世帯になると、医療・介護費負担が大幅に軽減されます。
窓口負担は 1割据え置き に加え、次のメリットがあります。
-
国民健康保険料:均等割・所得割の軽減あり
-
介護保険料:所得段階の引き下げあり
-
高額療養費制度:自己負担上限が低く設定
-
各種福祉給付(光熱費補助、公営住宅家賃減額など)対象になりやすい
2割負担 vs 非課税世帯(1割負担)の比較
| 月の医療費総額 | 2割負担 | 非課税世帯(1割負担) | 差額(年間) |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | +12,000円 |
| 20,000円 | 4,000円 | 2,000円 | +24,000円 |
| 30,000円 | 6,000円 | 3,000円 | +36,000円 |
| 50,000円 | 10,000円 | 5,000円 | +60,000円 |
👉 さらに「保険料・自己負担上限」でも差が広がります。
5. どう備える?実践ポイント
① 自分の戦略を決める
-
資産がある人 → 非課税世帯戦略(収入を調整して優遇を最大化)
-
資産が少ない人 → 繰下げ戦略(年金額を増やして医療費増に対応)
② 地域差を理解する
-
1級地(名古屋市など):非課税ライン=単身155万/夫婦211万
-
3級地-2:非課税ライン=単身145〜150万/夫婦195〜205万
👉 地方ほど非課税世帯から外れやすいので注意。
③ 医療費専用口座を準備
-
月1〜2万円を積立 → 10年で120〜240万円の“医療費備え”
④ 健康寿命を延ばす
-
運動・食事・睡眠・検診を徹底
👉 最大の節約は「病気にならないこと」
⑤ 制度は変わる前提で情報収集
-
ねんきんネット・市町村広報・厚労省発表を定期チェック
まとめ:結局どうすべきか?
-
妻が年下 → 65歳から年金受給開始(繰下げしない)、加給年金+非課税メリットを活用
-
妻が同年・年上 → 繰下げで年金増額、長生きリスクに備える
-
資産がある人 → 非課税世帯を狙い、制度優遇をフル活用
-
資産が少ない人 → 繰下げで年金を増やし、制度改正にも耐えられる現金収入を確保
👉 老後の安心は「制度をあてにする」のではなく、制度が変わっても対応できる準備をすることです。