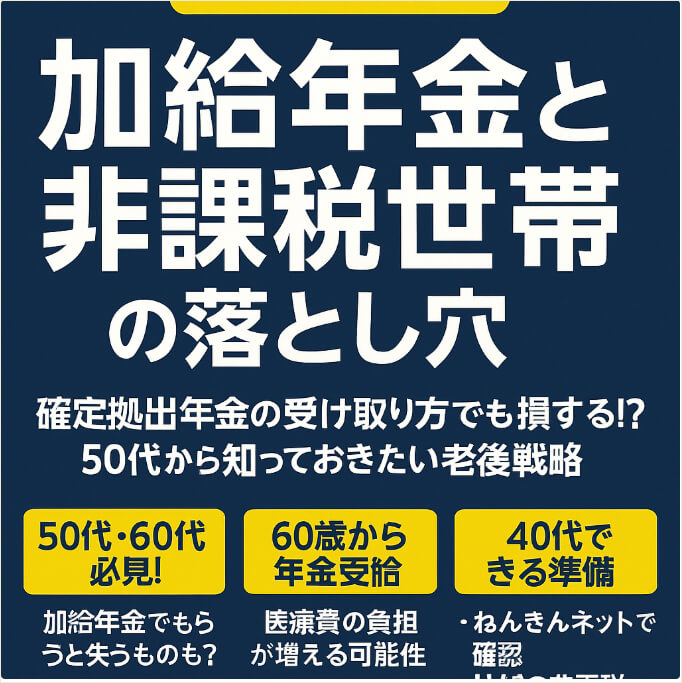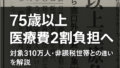~確定拠出年金の受け取り方でも損する!? 50代から知っておきたい老後戦略~
「ある日突然、年金が減った!?」
実はそれ、加給年金や非課税世帯の仕組みを知らなかったせいかもしれません。
50代・60代に必須の年金知識を、40代から準備できる形で解説します。
加給年金とは?
会社員時代の「家族手当・扶養手当」にあたるものが、年金生活に入ってからの 加給年金 です。
-
厚生年金に20年以上加入した人が65歳になったとき
-
生計を維持する 65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子 がいる場合
👉 年金に上乗せされて支給されます。
支給額(2025年度)
-
配偶者:239,300円/年
-
子ども(1人目・2人目):239,300円/年
-
子ども(3人目以降):79,800円/年
-
配偶者にはさらに 特別加算(35,400円〜176,600円)
いつまで支給される?
-
配偶者が65歳になるまで
-
子どもは18歳到達年度末まで
👉 いわば「子ども手当」の年金版です。
注意点:もらうと失うものもある
加給年金は一見プラスですが、もらうことで 非課税世帯から外れる ことがあります。
-
世帯収入が非課税ラインを超えると、
・医療費1割負担 → 2割負担に
・国民健康保険料・介護保険料の軽減が消滅 -
繰下げ受給を選ぶと、その間の加給はゼロ
-
失業保険や各種給付金にも影響
👉 加給がそのまま得になるとは限らない のが最大の落とし穴です。
非課税世帯と「壁」
非課税世帯になると税金が軽くなるだけでなく、医療や介護の自己負担が軽減されるなどメリット多数。
ただし、地域の「級地」によって基準が違います。
-
1級地(都市部):211万円以下
-
3級地(地方部):195万円以下
👉 同じ年金額でも、住む地域で「非課税かどうか」が変わります。
ケース別シナリオ
ケース① 加給あり(年金180万+加給24万=204万)
-
3級地 → 非課税ライン195万円超え → 優遇喪失
-
1級地 → 211万円以下なのでセーフ
ケース② 加給なし(年金180万のみ)
-
3級地でも195万以下 → 非課税世帯維持
👉 医療1割・保険料軽減が継続
ケース③ 確定拠出年金もプラス
-
公的年金180万+加給24万+確定拠出(年金形式24万)=228万円
👉 1級地・3級地ともに非課税を超え、優遇失う
👉 今はセーフでも、将来「非課税ラインの引き下げ」や「医療費2割負担拡大」でアウトになる可能性があります。
確定拠出年金の受け取り方シナリオ
シナリオ①:60歳から年金形式
-
公的年金+加給に合算 → 非課税世帯から外れるリスク大
シナリオ②:65歳から年金形式
-
加給終了後にプラスされるが、収入合算で非課税維持は難しい
シナリオ③:一時金で受け取る
-
退職所得控除を活用でき、非課税世帯判定には含まれない
👉 非課税メリットを守りやすい
40代からできる準備チェックリスト
✅ ねんきんネットに登録して見込み額を確認
✅ 配偶者の年齢差を把握(加給対象かどうか)
✅ 自分の地域の「非課税ライン」を確認
✅ NISA・iDeCoで医療費や介護費の備えをつくる
✅ 保険・携帯・住宅ローンなど生活固定費を軽くする
✅ 健康投資(運動・食事・睡眠)で将来の医療費を減らす
今後想定される制度改正
-
年金控除額の縮小(課税範囲が広がる方向)
-
医療費負担の拡大(1割→2割、将来は3割対象者増も)
-
非課税世帯ラインの引き下げ
-
国保・介護保険料のさらなる上昇
👉 制度は「今のまま続く」とは考えない方が安全です。
結論
-
加給年金は「年金生活の家族手当」だが、非課税世帯との兼ね合いで損得が変わる
-
確定拠出年金の受け取り方次第で、さらに大きく影響
-
制度改正を見越し、自分の収入構成・地域区分に合わせて最適化することが重要
👉 老後のカギは「制度に依存する」ことではなく、
制度の変化に対応できる自分になること です。